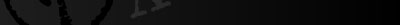*三人目「…お前のように賢しらな者が、このゲームがどれだけフェアじゃないか、わからなかったとでも申すか?」オレを見下ろす、その目。 かつてその視線には、オレに対する信頼や親しみも確かにあった。だが今は、怒りと嫌悪、そして蔑みだけがそこにある。 「…答えろ」 霊界の長の声もまた、ずいぶんと冷たい。 けれどそれもまた、どうでもいいことだった。 今となっては、全てがどうでもいい。 全てが、だ。 ***
それは、焦げつくような熱さだった。郊外の住宅地。二階建ての小さな一軒家。 築二十年ほどと土台は古いが、リフォームをしたことで、どこにでもある小綺麗な普通の住宅になっている。 庭と呼ぶのもはばかられるほどの小さなスペースには、花壇があり、花やハーブが植えられていた。 隣とも向いとも、もっと言えばこの辺一帯の家々とほとんど変わらない、何の個性もない家。 この家を、彼は遠く遠くから、じっと見つめていた。 焼き焦がすような熱い視線は、昼夜を問わず注がれていたのだ。 オレを見つめる、その熱さ。 この生活も、もう何年経ったことだろう。 ***
オレは読みやすいよう折りたたんだ新聞を手に、目の前に並べられた食事に目を落とす。目玉焼きにベーコン。レタスとトマトのサラダ、トーストとコーヒー。 彼女の作る食事は、彼女と同じくらいありきたりで、微笑ましいほどだった。 オレは笑顔で、それらを片付ける。 仕事や、人付き合いや、妻への愛情表現のように、よどみなく、関心もなく。 「今日も、遅くなるの?」 「そうだね。ちょっと厄介な仕事が続いていてね」 「そう」 少しさみしそうな顔をする彼女に、オレはすまなそうな顔を作って微笑む。 長めのショートヘア、女性らしいやわらかな曲線を描く体。全体的に薄化粧だというのに、マスカラで固めた睫毛だけが、作り物のようにピンと上を向いている。 十時から三時までのパートを終えれば、自分と夫の夕食を作るために買い物をして帰る、どこにでもいる女。 「ごめんね。夜は友達とご飯でも行ってきたら?」 「…そうだね、そうしようかな。一人分だと作るのもね」 自分の分のコーヒーを注ぎ、オレの向いではなく隣に彼女は座る。 結婚前からの彼女の定位置に。 カーディガンに包まれたやわらかな腕が、オレのワイシャツの腕に触れる。 「秀ちゃん」 弁当の包みを差し出しながら、彼女が言う。 誰のことを呼んでいるのかというという呼び名も、もう慣れたものだ。 「秀ちゃん、あのさ」 働きすぎは良くないよ。 頑張っているのはわかるけど、体を大事にして。 家のローンとか、そんなのどうにでもなるんだからね。 月並みな言葉。 月並みな女。 かわいい女だ。 かわいいが、かわいいだけで何の役にも立たない、ペットのような。 「ありがとう。麻弥」 嬉しそうなその顔。 薄く口紅の塗られたその唇に、コーヒー味のキスをした。 ***
弟が遠方の大学に入るために家を出たのを機に、一軒家に夫婦二人では無駄が多いと、両親は義父の職場の近くに2LDKのマンションを買った。狭いながらも、両親はそこで仲良く暮らしている。残された、古い一軒家。 手放すには思い出が多いと躊躇う母に、結婚を控えていたオレに、リフォームしてここに住まないかという提案がなされたのは自然な流れだ。 いずれ子供を持つなら、一軒家がいいだろう、と。 結婚。 子供。 死ぬほど馬鹿馬鹿しい。 そんなものを欲するのは、短い寿命にあがき、どうにか自分の生きた証を残さねばと必死になる人間だけだろう。 それを受け入れたのは、無論母のためでしかない。 麻弥と結婚したのも、子供がちゃんと結婚したという安心と、血の繋がった孫を抱く喜びを母に与えてやるためでしかなかった。 満員電車に揺られながら、またあの熱さを感じていた。 髪に、頬に、背に、視線を感じる。 彼がオレを、見ている。 ***
「やあ」十二階。夜のオフィス。 青い光りを放つパソコンが、時刻は十時半だと告げている。 窓もろくに開かないのがビルというものだが、この部屋だけは窓が開くように細工をしてあった。 彼がここに、来れるように。 窓枠に黒いブーツが、トンと降りる。 細く開いた窓から、彼は器用に体を滑り込ませた。 「久しぶりだね」 この間彼にあったのは、三日前だ。 久しぶり、というほどの時間ではない。けれど、きっとオレ以上に、彼は時間を長く感じている。 「おいでよ、飛影」 無言で窓辺に佇んでいた彼が、無言のままオレに歩み寄る。 黒いコート、黒いズボンに黒いブーツ。砂のような風のような、乾いた魔界のにおいを微かにまとわせて。 十時半。 一時間ほどセックスをし、終電に乗って帰ることのできる、オレにとっては都合のいい時間。 タクシーに乗る金は存分にありながらも、オレは電車に乗って帰るのだ。人間ごっこのルールに則って。 この時間のフロアにもう人気はない。 血は繋がらないとはいえ社長の息子であるオレに、与えられた仕事部屋は個室だ。 今はオレと飛影の、セックス部屋でもある。 すぐ目の前に立った彼の腕をぐいと引き、椅子に座ったままの自分の膝に座らせる。 大きな赤い瞳に映るオレは、麻弥の選んだネクタイをし、麻弥の作った食事を食べて、麻弥とセックスをしている、オレだ。 ***
ブーツとズボンを脱がしながら、四年前のあの日を思い出す。オレは彼に選ばせた。 彼の意思で、選べばいいと。 「待ってろとは、言わないよ」 母のために、人間界で暮らし、人間の女と結婚する。 結婚し子を作り、母が寿命を全うした後は、女と子供はもちろん、関わった全ての人間の記憶を消し、魔界へ帰るつもりだ、と。 「どうする?まあ、せいぜい長くて五十年ってとこだけど」 魔界の隠れ家の一つで、いつものように長い時間をかけたセックスの後。 隣に横たわる彼の髪を撫でながら、オレは彼に選ばせた。 飛影と、いわゆる、人間界風に言うところの“付き合っている”状態になってから、もう五年が経っていた。 オレと別れるか。 それとも五十年の間、離れるか。 あるいは、五十年間、それでもオレの側にいたいのか。 人間界にわざわざ出向いて、オレに抱かれたいのか。 冷笑し、あっさりと別れを選ぶか、五十年後に気が向いたら会ってやるとでも言うか、多分、そのどちらかの答えをオレは予想していた。 白いシーツの上でのろのろと起き上がった彼は、意外な選択をした。 待つ。 そう言った。 驚いたことに、魔界に来れないのならば自分が人間界に会いに行くと、オレと目を合わさずに、呟くように言った。 オレが会いに行く、無意識にきつくシーツを握り、飛影はそう言った。 大きな赤い瞳、小さな口、どこもかしこも白い、幼いままの体。 あの時の気持ちを正直に、そして一言で言うならば、優越感。 まさに優越感だった。 プライドが高く、口説いてもなかなか落ちなかった飛影。 長いことオレに自分を追わせ、山ほど浴びせた愛の言葉に、居心地悪そうに頬を赤らめていた、飛影。 それが、このザマだ。 別れを切り出され、追いすがるとは。 そんな心の内を誰かに言ったならば、人の心を持たぬ下衆な野郎だと、罵倒されることだろう。 もっとも、待つと呟いた時の飛影の表情、会いに行くと消え入るような声で言った飛影の、俯いた白い首筋。 まったく、あの感情は優越感としか言いようがなかった。 ***
向かい合い、椅子の上で。それがここ何年かの、オレたちのセックスのスタイルだった。 飛影はブーツとズボンだけを脱ぎ、コートは着たままで。 オレはズボンを膝まで下ろし、後はネクタイを緩めるだけだ。 肘掛けに飛影の両足をかけさせ、無骨なオフィスチェアを激しく軋ませる。 このフロアの照明は消されているが、都市の夜に闇はない。 隣りのビルのまだ灯されている明かりや、けばけばしい看板のネオンが、下品に部屋を照らし出す。 「あっあっあっあっ!…んん…ふ…ぅ」 「…飛影……飛影」 椅子は耳障りに軋み、黒いコートの背が、デスクの縁に触れる。 いったいこの椅子は、何度この用途に使われただろうか、などと考える。 コートだけを着ている彼は、黒いワンピースを着た少女のようにも見えた。 もちろん、ここである必要などない。ホテルにでも行けばいいのだ。 なんなら彼との逢瀬のために、部屋を借りたっていい。 けれど、そのどちらも彼は不要だと言った。 ここでいい、と。 「あっ!…あう、うう、あ、あ…」 息と一緒に漏れるような、濡れた声。 きつくきつく締め上げる、狭く熱い体内。 これがセックスならば、麻弥とのそれは、本当にクズのようなものだと、しみじみ思う。 「っふぁ…あ、あ、あ…ああ、くら…ま…蔵馬…っ」 オレの股間に尻を激しく打ち付けながら、飛影はオレの名を何度も呼ぶ。 以前よりも、ずっと多く、オレの名を呼ぶようになったことに、彼は気付いているのだろうか。 肌の表面はひやりと冷たいのに、彼の中は驚くほど熱い。 「…飛影…いいよ…もっと」 「くら…ま!…んん!…蔵馬……蔵馬…っ」 パソコンの微かな電子音と、オレたちの呼吸する音だけだった室内を、甲高い電子音が乱した。 激しい動きが、ぴたりと止まる。 飛影の両手が、オレの髪をぎゅっと握る。 無機質な電子音。 デスクの上で鳴り響く携帯に、飛影の顔がみるみる青ざめる。 青ざめた頬にキスをし、携帯を取り、微笑んで見せる。 「麻弥?どうしたの?」 ぐうっと、痛いほどに体内が締まる。 髪から指を解いた飛影が体を離そうとしたが、それを許さず、大きく突き上げる。 「電話してくるなんて、めずらしいね」 「………っん」 「そう。良かったね。今度オレも連れて行ってよ」 「ぅ……」 包帯をした右手の甲で、飛影は口を塞ぐ。 真っ赤な目を見開き、いやいやする子供のように頭を振り、尻を持ち上げなんとか抜こうとしている。 「結婚記念日?だいぶ先じゃない。そんなこと言わずに来週にでも行こう」 肩と耳とで携帯を挟み、空いた手で、コートの中を探る。 勃ち上がっていたものを握り、ゆっくりと上下にしごいてやる。 「…っ…ん!」 包帯の上から手を噛みしめ、飛影は目を閉じる。 親指の付け根、ふくらんだその部分に、じわりと赤い染みが広がった。 電話の向こうの人間に、声を聞かれまいとする、いじらしさ。 包帯を染める彼の血に興奮し、オレはますます激しく突き上げる。 「……っ…っ!!」 「うん、終電で帰るよ」 「…っ……ふ」 「え?今じゃなく?帰ってから?」 早く帰ってきて。いつもなら言わないようなことを、彼女は言う。 飛影を抱いているオレの耳に、電話ごしの麻弥の声は、なぜかそわそわしているように感じた。 「わかったよ。今日はさっさと片付けて帰る」 それは、仕事を片付けて、という意味だった。 だが、オレをくわえ込む飛影の尻は跳ね上がり、小柄な体をぶるりと大きく震わせた。 「仕事中に電話をしてくるほど、馬鹿な女じゃないはずなんだけどな」 通話を終えた携帯をデスクに放り投げ、飛影の口元から傷付いた右手を外す。 口元を押さえる手が外れ、飛影は肩を上下させ、大きく息を吐いた。 「……っ、ふ、あああぁ…」 「気にしなくていいのに。聞こえやしないよ」 「…んっんっんっ…あ、ああ」 また、椅子が軋む。 オレの上で体を上下させたまま、飛影はオレから目をそらし、窓の外へと視線を移す。 点滅するピンク色のネオンが、白い肌をチラチラ照らす。 「………くら…ま…蔵馬……蔵馬」 「飛影……好きだよ…飛影…」 君が好き。 君を愛してる。 五十年なんて、オレたちにとってはほんの一瞬さ。そうだろう? 耳元で囁き、唇を重ね、薄い背を抱きしめ、何度も何度も抜き差しを繰り返す。 揉みしだいたコートの前はすっかり濡れ、布はくたりと飛影を覆う。 熱い。 きつい。 気持ちいい。 「……っ…くら…ま…!あああぁぁぁ」 細く甲高い声が、部屋を震わせる。 のけ反った白い喉に、強く吸い付いた。 ***
それは、朗報だった。パジャマ姿で玄関へ小走りに駆けてきた麻弥は、スーツのままのオレに真正面から抱きついてきた。 「ただいま。さっきの電話、なんだったの?」 なんだったのかと聞きつつ、オレはだいたい予想はできていた。 わざわざ電話をかけてきておきながら、やっぱりいい、後にする、帰ってきてからね、と彼女は言った。 わかりやすい女は、こんな時までわかりやすい。 「おかえり!……あのね…あのね、秀ちゃん、パパになるんだよ」 ステップ2、完了というわけだ。 頬を紅潮させ、興奮し目を輝かせている麻弥を引き寄せ、高く抱き上げた。 幸せそうな笑い声を上げ、オレの髪に指を絡める女。 ついさっきまで、別の者がこの髪に指を絡めていたなど、知る由もない。 オレもまた、嬉しくてたまらないとでもいうように、女を抱きしめ、キスを降らせる。 髪に、頬に、唇に。 「ねえねえ、男の子かな、女の子かな?」 「もー、秀ちゃんてば。まだわかんないよ。どっちがいいの」 「どっちも欲しいな。いっそ双子でもいいくらい」 オレの愛する双子の兄の赤い瞳が、ふっと脳裏をよぎる。 ステップ2完了だよ、飛影。 もちろん心の中だけで、呟く オレのために夕食を温め直しながら、麻弥はひっきりなしに喋る。 男の子だったら…女の子だったら…実家の近くに評判のいい産院があるの…お義母さんたちに報告するのはもうちょっと待ってね…従姉妹が素敵なベビーチェアを買ってたから同じの欲しいな…キャラクターとかアニメの服は着せたくないからシンプルでかわいい服を着せてあげて…お休みの日にはみんなで… 笑みを絶やさずに、オレは全てに同意する。 どうだっていいことに、反論などあろうはずもない。 産まれてくる子供は、妖力を封じるつもりだった。 半妖と人間の子では、多分寿命は短いだろう。もっとも、母さんが生きている間だけでいい。三十歳ぐらいまで生きてくれれば役目は十分果たす。 焼き焦がすような熱い視線が、またオレに注がれる。 立ち入り禁止のあのビルの屋上で、彼はオレを見ているのだろう。 まだ続いている話に笑顔で相づちをうちながら、温めすぎて香りの飛んだ味噌汁をすすった。 ***
二か月ほど、飛影は姿を現さなかった。額の目でオレを見つめる、あの視線もない。 まあ、彼には彼の仕事もある。 二か月前まで三日と空けずに人間界に来ていたのだ。パトロールをさぼるなと躯に叱られたのかもしれない。 単純に、恋人が訪ねてこないというのが理由なのだが、以前よりもオレは、早く帰宅するようになっていた。 妊娠した妻を気遣って、と周りには見えていることだろう。 青い光りを放つパソコンが、時刻は七時半だと告げている。 結婚記念日の今日は、麻弥が行きたいと言っていた店で夕食をとることになっていた。 手早く仕事を片付け、待ち合わせの店へ向かう。 会社から電車で六駅。 八時の予約を取っておいたスペイン料理の店は満席で、オリーブオイルやニンニクの匂いが店中に立ち込めていた。 だが、麻弥はまだ着いていなかった。 女というものはえてして時間に遅れがちなものだ。シェリー酒を舐めながらオレは待っていたが、八時を十五分ほどまわったところでさすがに席を立ち、ウエイターに携帯を指差して合図をし、外へ電話をかけに出た。 古くさい女の声が、ただいま電話に出ることができません、というメッセージを耳元に吐き出す。 どういうつもりかと、オレは腹立たしく電話を切る。 その瞬間。 焼き焦がすような熱い視線が、オレに突き刺さった。 ***
タクシーを飛び降り、道路から玄関まで、ほんの五歩のアプローチ。鍵を開ける前から、覚えのある、生臭いような錆びたような臭いが鼻をつく。 よく知っているその臭いは、玄関を開けた途端、むせるような強さでオレに襲いかかった。 「麻弥…!?」 見開かれた目。硬直し、薄笑いのように引きつった口元。 転がる死体は、確かに今朝までは妻だったものだ。 オレはぐるりと、玄関から家の中を見渡す。 茶色の床も、白い壁も、結婚祝いで誰かがくれた水辺を描いた絵も、何もかもが真っ赤に染まっていた。 人間ひとりの血が、これほど大量だとは知らなかった。 こんな時なのに、そんなことを考える。 「……麻弥」 彼女の腹部は十字に切り裂かれ、あふれ出した内臓が、嫌な臭いをまき散らしている。 ふと、こちらに向けて伸ばされているかのような彼女の左手の、薬指がないことに気がついた。 同時に、その薬指が、玄関に並べられたスリッパの中に転げていることにも気付く。 血の足跡をたどるように、よく知る妖気のもとへと進む。 ダイニングキッチンのテーブルには、黒い影。 四人掛けのテーブルの、手前の左側。 麻弥の定位置のそこに、彼はいた。 右手には血塗れた剣。 左手には、白いマグカップ。 それはオレたち夫婦が、いつもコーヒーを飲むのに使っているお揃いのマグカップだ。 白いマグカップには、赤くべっとりと指の跡が付いていた。 「…………飛影」 こちらを見ない飛影の手の中。白いマグカップ。 そこには無論コーヒーはなく、得体の知れないぐちゃぐちゃとした肉片が、どろりと醜悪な姿を見せている。 「飛影!!!!」 ゆっくりと、飛影が振り向く。 オレを見上げる赤い瞳は、高熱に浮かされる病人のようだった。 「飛影!! お前…っ!?」 飛影の薬指。 そこにはめられた、見慣れた指輪。 プラチナの結婚指輪は、確か7号だった。 小柄だが、しなやかな筋肉でできていたはずの彼の体。 7号の指輪が薬指にはまるほど、彼が痩せたという事実に、その時ようやくオレは気付いた。 この四年間、それに気付きもしなかった。 「あ……ああ…っ……飛影!おい…!」 血で汚れた左手が、マグカップを差し出す。 その肉片が何なのかようやく理解し、全身に鳥肌が立つ。 剣を握ったままの右手に、力が込められるのが、見えた。 「………おかえり」 いっそ優しいといってもいいくらいに、やわらかな、声。 ぎらりと禍々しく剣が光る。 止める間は、なかった。 一瞬で、 飛影は自分の首を 切り落とした。 自分の叫び声が、耳に痛い。 凄まじい勢いで噴き出した血は、視界を遮るほどだった。 「………ひ……えい…?」 飛ばされた首は、テーブルの上で一度跳ね、オレの足元に転がり落ちた。 オレを見上げるような位置で、ごろりと首は止まる。 「……ひ」 ゆっくりと閉ざされていく赤い瞳から、 一粒だけの氷泪石が、 血の海に、零れ落ちた。 ...End. トロイリズム(三者性愛) 夫婦や恋人関係において、第三者が加わる状況への性的嗜好。トリオリズムとも言う。パートナーを第三者へ晒す性的嗜好の「カンダウリズム(英語:Candaulism)」も参照のこと。英語:Troilism または Triolism |
Copyright RUMeRAL all rights reserved.
Since 2013 January
Since 2013 January