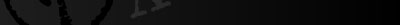*彼の俺「あんまり食べないんだね」俺の用意した夕食は宅配のピザとポテトとコーラという子供の喜びそうなメニューだったが、飛影はろくに食べなかった。 「小食なの?」 返事はない。 冷めかけているピザの隣には、ケーキが入っているらしい箱がある。飛影が母親に持たされてきた物だ。 ー本当に、いいんですか? 数日前、彼の母親は嬉しそうに、けれど申し訳なさそうに、電話越しに俺に尋ねた。 お友達の…いえ、先生をお友達なんて呼んじゃいけないわね。あの子が誰かのお家に泊まりに行くなんて初めてなんです。 小さい頃からあの子はいつもひとりぼっちだったし、一人っ子だし、誘ってくれるお友達もいなかった。 先生は優しいわ。え?そんなことないって?いえ、わかってるんです。だって、大学生のあなたには中学生の相手なんて退屈な子守でしかないでしょう?でも、本当に嬉しい。 女性にしては低いが甘く、心地よい彼女の声をさえぎって、俺は笑った。 「いえそんな。ただ家でピザでも食べて、借りてきた映画でも一緒に見ようと思っているだけですよ」 「あの子、喜ぶわ。私は和食しか作れなくて」 和食、ねえ。 自分で言うのもなんだが、俺の料理の腕はなかなかだ。 けれど、俺は彼に食事なんか作ってやらない。 栄養も何もないジャンクフードだけを食べて、小さいままでいればいい。 「本当に気にしないでください。俺も一人っ子ですから弟ができたみたいで楽しいですよ」 弟。 自分で言っておいて、おかしくてたまらない。 なにせ、その“弟”を犯そうとしているのだから。 ***
ケーキの箱を手に下げて来た彼は今、俺の部屋で、冷めたピザの前で、俺とは目を合わさずにコップの氷を見つめている。「もう少し食べたら?」 今日の彼は、一層無口だ。 その理由はよく分かっているのだけれど。 「何?俺とセックスするって考えたら緊張しちゃって食べれないとか?」 カチン、と音を立てて、氷が揺れる。 飛影がこちらを睨んだ。 真っ赤な瞳、大きな瞳で。 「……腹が減ってないだけだ」 震える手をサッとコップから離し、テーブルの下に隠したことなんて俺にはお見通しなのに。 「そう。じゃあ片付けるね。シャワー浴びてきたら?」 その言葉に今度こそ、飛影の肩がはっきり震えた。 ***
かわいいな。彼のことを“かわいい”と思うのは一体何度目だろうか。 まったく、日に日にかわいくなるようだ。 シャワーを浴び終わった俺が部屋に戻ると、俺が用意しておいたパジャマを着た彼はテレビもつけずにベッドの上で枕を抱え、ただ硬くなっていた。 「飛影」 痩せた肩に腕をまわす。 小刻みに震える体は、シャワーの後だというのにもう冷たくなっていた。 「どうする?飛影」 彼は、本当に小さい。 立って俺と並ぶと胸まで届かない所を見ると、身長は130センチほどだろうか。 俺を見上げるその上目遣いに、今すぐ突っ込んでやりたい衝動に駆られる。 「本当に、する?」 逃げ道があるように思わせて、追いつめる。 あくまで自分で選択したことなのだと、彼に思わせるために。 追いつめられた小動物の心臓は、きっと激しく跳ねているのだろう。 「……ああ」 「するんだね?」 「……そう言っただろうが」 聞こえなかったのか?耳が遠いんだな。 幼い顔で、眉間に皺をよせて、憎まれ口を叩く。 短い髪をかき上げ、額にキスを落とす。 「脱いで。飛影」 ***
パジャマのシャツから脱ごうとした彼を止め、下だけを脱がせた。上半身になど用はないのだと、知らせるように。 こわばっている体をうつ伏せ、四つん這いにする。 「お尻を高くあげてごらん」 顔をベッドに付けさせ、尻を高く上げさせる。そのまま軽く足を開かせると、それだけで小さな穴は丸見えになった。 両手でギュッと握った枕に顔を埋め、震える尻をこちらに向けたその姿。 毛のないつるりとした陰部。 真っ白い尻の中央だけが、ピンク色に色づいている。 するっと尻を撫で、絹のような手触りを楽しむ。 用意しておいたローションの蓋を開け、指にたっぷりとつける。 伸縮性があるとはいえ、指一本入れるのがやっとのようにさえ見える小さな穴。等間隔に皺がよっていて、中央の濃いピンクから外側の薄いピンクへと、綺麗なグラデーションだ。 ローションにぬめる指で、つ、となぞると、ビクリと尻が揺れた。 指先で、円を描く。 筋肉の輪が緩むよう、揉みほぐすように。 クチャクチャと音を立て、指先を動かす。 そろそろ、いいかな。 「……っ…ひ…」 人差し指の先端を、穴に沈める。 大きさ的には座薬とそう変わらないはずだが、枕に顔を埋めたまま、小さくくぐもった声を彼は漏らした。 構わずに、続ける。 抜き差しを繰り返しながら、人差し指を根元まで納めた。 「……っ、ふ、ぁ」 「俺の指が入ってるの、わかる?」 途端に、指がギュッと締め付けられる。正直な体。 それから五分程かけて、二本の指を納めた。中の赤い粘膜が覗くたび、喉がなる。 狭いアパートに、彼の吐息と、俺の指先が立てる水音だけが響く。 「……っ、ぁ……は」 「体、起こすよ。飛影」 慣らすために四つん這いにしたが、入れる時は仰向けにするつもりだった。 初めての彼がどんな顔するのか、目に焼き付けなければ。 軽い体をぐいっと返す。 両手で握りしめたままの、枕を取り上げた。 白い頬は高熱に浮かされているかのように染まり、赤い瞳は潤んでいた。 「………くら」 俺は着ていたTシャツを脱ぎ捨てる。 「口で、してくれる?」 小さな手を股間に導き、盛り上がったそこを、ズボンの上から触らせる。 引っ込めようとする手を許さず、形や大きさがよく分かるように、押し付けた。 「……いや……嫌、だ」 「そう?まあ今日はお尻を使わせてくれるんだからいいけど」 ズボンも脱ぎ捨て、口でしてもらうまでもなく勃っているそこを、飛影に見せてやる。 女顔だとよく言われる俺だが、ズル剥けのそこは我ながら立派なものだ。 「………っひ」 飛影が小さく声を上げ、視線を反らした。 頬の赤みがすうっと引く。恐怖と羞恥に、血の気が失せていく。 抱え上げた両足を大きく広げ、肩に乗せる。 ぬるつく穴。指で広げたそこに、先端を押し付ける。 こわくてこわくてたまらないだろうに、唇を噛みしめ、飛影は健気にも逃げ出そうとはしなかった。 それほどまでに俺に嫌われたくないのだろうかと、いじらしく、愛おしい。 「……うっぐ、う!」 先端が、ぐにゅっと穴を開く。 皺の寄った穴が、大きく引き伸ばされる。 「……ん!あ!…ぐう!! あ」 「大声、出さないでくれない?」 このアパート、音が結構筒抜けなんだよね。 強姦されているみたいな声上げられちゃ、困るよ。 俺の心無い言葉に失望を隠せないでいる飛影の口を、手のひらでふさぐ。 あたたかく濡れた吐息が、手にくすぐったい。 「ん!んん……んーっ!!」 半分ほど入った所で、結合部が赤く染まった。 小さな穴の何ケ所かが裂け始めたのだ。 「んっう!! う!うう!! ん、う!んんーーーーっ!!」 とうとう、抵抗し始めた。 両手で俺の肩を叩き、押し返し、必死で俺の下から逃れようとする。 穴が押し広げられ、裂かれる痛みに、真っ赤な瞳がぼろぼろと涙を零す。 優しい言葉のひとつもかけて、もっとゆっくり入れてやればいいのだろうが、そうはしない。 「んんーーーーっ!! んんーーーーっ!! うう!」 「いいよ…飛影。君の中、とっても気持ちいい」 それは本当だ。 狭くてきつくて熱いそこを押し広げるのは、素晴らしい快感だった。 ローションの人工的な香りを圧倒する、飛影の血の匂いも。何もかも、素晴らしい。 「ぁんんーーーーっ!!うううううん!っん!!」 グジュ、と音を立て、根元まですっぽり納まった。 口をふさいでいた手を、そっと放してやる。 「……ひ、あ、ぁ……う」 「いい子だね。全部入ったよ」 白いシーツ。 飛影の尻の下の部分は、真っ赤に染まっていた。 「……ぁ、あ…いた…い…痛いっ…蔵馬…い!」 抜いて、差して。 彼の尻にぶつかる、パン、という音。 「い、あ…嫌……くら…!」 大声を出すなと俺が言ったことをちゃんとおぼえていて、悲鳴を上げまいと唇を噛みしめている、涙と涎でぐちゃぐちゃの顔。 嗚咽の度に、きつくきつく、中が締まる。 「…う…うう、あ……」 飛影は少しも快感など感じてはいない。 その証拠に、小さなチンコは萎えたまま、律動に合わせてただ揺れている。 「……あ……あ…あ」 青ざめた顔。 泣きながら、されるがままになっている小さな体を突く。 何度も、何度も。 「……ぅう…ぁ」 「中に、出してもいい?」 もう、何を聞かれているのかもよくわからないのだろう。 返事を待たずに、俺は大きく腰を揺らし、ぐうっと奥を突き、射精した。 元々大きな瞳がさらに見開かれ、噛みしめた唇に血が滲む。 直腸に射精されるというのがどういう気分なのか俺には分からないが、浣腸みたいで気持ちのいいものでもないだろう。 ずるっと引き抜いたそこからは、今し方注ぎ込んだばかりの精液と、大量の血が流れ出した。 細い両腕が、力なくシーツに落ちる。 「……ひ、あ…あ、くら…」 ハッハッ、とひどく忙しない呼吸を飛影は繰り返す。 「ひ、あ…っう…っ!…苦し…息、が…でき…」 喉元を抑え、飛影は身を捩った。 どうやら、痛みとショックに過呼吸をおこしたようだ。そういう子は、前にもいた。 「……や、うあ、ぁ、っは」 飴とムチ。 結局、何を教えるにしたって、それが必要なのだ。 呼吸ができずにパニクってもがく体を見下ろし、俺は微笑んだ。 「飛影」 のたうつ体を押さえ、仰向かせる。 唇を合わせ、息を吹き込んだ。 厳しい授業の後には、ご褒美が必要だ。 そうだろう? ***
溺れる者が救助者に必死ですがるように、飛影は俺にしがみついている。彼の目にはきっと、俺が救いの神のように見えただろう。 息ができないという恐怖と苦痛から、あっという間に救ってやったのだから。 「……あ、っは…くら…ま」 「飛影、ゆっくり深呼吸をして」 過呼吸の手当てなんて簡単なものだ。 紙袋でも口に当てて、呼吸をすればいい。それもできないほど相手がパニクっている場合は、こうして息を吹き込んでやればいい。 「良くなったでしょ?」 こっくり、頷く。 びっくりして丸くなった目で、俺を見つめながら。 「……蔵馬…今、の」 「君って、本当に俺がいないと駄目なんだね」 着たままだったパジャマのボタンを外しながら、俺は優しく話しかける。 「俺が側にいてあげなきゃ、息もできなくなって死んじゃうんじゃない?」 貧相な上半身。 あばら骨の浮いて見える、痩躯。 白い胸にぽちんと浮いた、これまた小さな乳首を唇ではさむ。 「……っ、蔵馬!?」 「じっとして…」 両の乳首をかわるがわる口で愛撫する。 舐め回し、軽く歯を立てる。 「……あ、ひあっ…!」 あっという間に、飛影はシーツにどろっとしたものを放った。 「……ぁん、ん」 乳首をくわえたまま、今度は包茎チンコをこねくりまわしてやる。 三か所に与えられる刺激に、飛影はたちまち俺の手を濡らす。 「んんっ、あ!蔵馬…!」 俺はまだ手を放さない。 皮から顔を出した亀頭をこすり、爪を立て、もう一度イカせる。 「…蔵馬…くら、あ、もう…や…ぁ…嫌だ…」 四回イカせた所で、飛影がまた泣き出した。 太股はぶるぶると痙攣し、乳首は真っ赤に腫れ上がっている。 「どうして?気持ち良くない?」 「……っい、あ…いい…けど」 「けど?」 こわい。 息も絶え絶えにそう呟く彼は、いつもよりもっと幼く見えた。 「心配しないで…俺にまかせて」 足を開かせ、股間を汚すどろどろの液体を、綺麗に舐め取ってやる。 袋を転がし、先端を甘く噛み、何度でも高みに追い上げる。 「ア、ア、アアア…ン!」 とろんと惚けた顔。 半開きの唇から、つっと一筋、涎が伝う。 ご褒美は、お気に召したらしい。 飛影に気付かれないよう、再びローションのボトルを傾け、指に絡める。 そっと、ゆっくりと、傷付いた肛門に指を一本だけ差し込んだ。 「ヒアッ…!!」 跳ねる体をなだめ、中を探る。 ぬるぬると指先を動かし、シコリを見つけ出し… 「アアアアアアン!!」 このアパートは音が筒抜けだと言ったのは本当だ。 両手のふさがっていた俺は、キスで口をふさぐ。 左手でチンコを、右手で直腸を弄り、立て続けに二度イカせる。 「……もぅ…出な…いって、言っ…や」 ぷつりと言葉を途切れさせ、小さな体は俺の腕の中に崩れ落ちた。 ***
閉め忘れたカーテンから降り注ぐ陽射しに目が覚めた。昨夜のうちにシーツを替えた狭苦しいシングルベッドで、パジャマを着せておいた飛影は俺の腕の中にすっぽり入り込んで眠っていた。 疲労を色濃く残した顔色はいいとはいえなかったが、ぐっすりと眠り込んでいる。 ズボンを下ろして薄い尻の肉をそっと開き、昨夜、薬を塗ったガーゼを詰めておいた傷口を朝の光の中で確認する。 裂けた傷は痛々しかったが、どうやら出血は止まったようだ。 コーヒーを淹れ、ピザの残りをオーブントースターに放り込む。 立ちこめるコーヒーとチーズの匂いに、ベッドがもぞもぞと動いた。 「……蔵馬」 起き上がろうとした飛影は、うっと小さく呻くと、ベッドに突っ伏した。 「……っつぅ…っ…」 「いいよ寝てて。持ってってあげる」 トレーに皿とカップをのせ、ベッドに運ぶ。 昨日手付かずだったケーキも一緒に。 「おはよう」 差し出したカップを、飛影はまるで初めて見る物のように、こわごわ受け取る。 昨日のご褒美に、ちゃんと牛乳も砂糖も入れてあるというのに。 ちゃんと座るのも辛いらしい彼のために、尻の下に枕を入れ、俺に寄りかからせてやる。冷めないうちにと俺はさっさとピザを口に入れたが、飛影は両手でカップを抱えたまま、手を付けようとしない。 「気分はどう?」 「……」 いいわけもないだろうが、彼は答えない。 「お尻、痛い?」 聞くまでもない。座れないほど痛いのだから。 ようやく口を開けた飛影は、甘ったるいコーヒーを一口含み、飲み込んだ。 俺に嫌われるのが怖い。 俺を失うのが怖い。 ひどく痛い目にも遭ったが、あの後の気持ちよさも忘れられない。 あれを失うのも、嫌だ。 それよりなにより、好きだから。 どうしようもなく、好きだから。 彼の心が手に取るようにわかって、吹き出しそうになる。 「ねえ、飛影」 小さな口は、もう一口、コーヒーを飲む。 「俺の恋人に、なりたい?」 ぱちゃん、と、コーヒーが揺れ、毛布にこぼれた。 昨夜と同じように、白い手は震えている。 「飛影?」 俺を見上げる瞳。 さびしい、心細い、子供の瞳。 「………り、たい」 「聞こえない。もっと大きな声で」 頬が触れるほど顔を近付け、俺は囁く。 「ほら、飛影?」 「……俺は…な…りたい……なりたい…!」 「そう。じゃあ…」 ケーキのクリームを指ですくい、飛影の口に押し込む。 「飛影。大きく、ならないでね」 このまま、小さいままいて。 130cmの、この体で、この顔で、この声のままで、いて。 「ね?飛影」 力の抜けた手から落ちそうになっていたカップを、俺はそっと取り、トレーごと床に下ろす。 呆然としている彼を横目に、俺はケーキの苺を口に放り込む。 熟していない苺はずいぶんと酸っぱくて、彼に似ている。 白い手が、すうっとのばされる。 俺に殴りかかるのかと思った手は、俺の背に回された。 「……飛影?」 「…ならない」 「え?」 大きくなんか、ならない。 俺はずっとこのままでいるから。 だから。 「お前は……俺のものだ」 痛む尻をひきずるようによたよたと、飛影が俺の膝によじ登る。 ぺたりと尻を落とすと、真正面から俺を抱きしめた。 体温の高い、子供の体。小さな、体。 ぽたぽた落ちる飛影の涙に、俺の肩あたりが濡れていく。 …ああ。 俺はうっとりと、目を閉じる。 手に入れた。 丸ごと全部、この子を手に入れた。 二三年も経てば無効になるような約束をしようとしている、愚かで哀れで、愛しいこの子を。 いずれ捨てられることを本当はわかっているくせに、わからないふりをしようとしている、この子を。 「いいよ…俺は君のものだよ」 膝の上に抱き上げた体を、ぎゅっと抱きしめ返す。 かわいいかわいい、俺の飛影。 君が大きく醜くなるまでは、俺は側にいてあげる。 いつかくるその日まで、俺は君のものだ。 「好きだよ、飛影」 ようやく与えた言葉に歓喜の色を浮かべた赤い瞳に、そっとくちづけた。 ...End. ペドフィリア(小児性愛) 主に11歳〜13歳頃の少年や少女への性的嗜好。現在では一般的に、年齢や性別を区分した「インファノフィリア(幼児性愛)」や「ニンフォフィリア(児童性愛)」なども含む総称として普及している。英語:Pedophilia |
Copyright RUMeRAL all rights reserved.
Since 2013 January
Since 2013 January