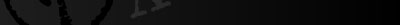*女神びちゃり。オレの丸めた手のひらの中に、温かいものがどろっと吐き出される。 今日だけで何度目になるかわからないそれを、オレは見下ろした。 ろくに食べていないせいで、固形物の見当たらない、吐瀉物。 それをオレの手に吐き戻した本人は、苦しさに肩で息をし、腹を抱えるように丸くなっている。 「うぇ…っ…げ…ぅっ…」 もともと小さいその体が、今は一回りも小さくなったかのように見える。 綺麗についていた筋肉は削げ落ち、見る影も無くやせ細った、体。 「飛影」 オレの呼ぶ声など、聞こえているのかどうか。 乱れた呼吸はせわしなく、白い指が短い黒髪をかきむしる。 「ゆき…な……ゆきなゆきなゆきなゅ」 泣くのでもなく、 怒るのでもなく、 彼はただ、狂った。 妹の死を、知らされて。 ***
あのガキをどうするのかは、お前次第だ。躯がオレに言霊を寄こしたのは、ひと月ほど前だ。 妹の死を知った飛影は、文字通り“狂った”そうだ。 笑い出したかと思えば、自分のいる場所がどこなのかもわからないかのように呆然と座り込み、次の瞬間には金切り声を上げて自分の体に剣を突き立てた。 何を食べさせても飲ませても嘔吐し、みるみる痩せ細るその姿に、放り出すのは忍びないと部下たちに面倒を看させていた躯も、根を上げたのだ。 パトロールどころか一人で部屋においておくこともできない有様に、お前が世話をするか、こいつを殺すかどっちかだ、と呼び出しに応じて百足に訪れたオレに、躯は言い捨てた。 「ここは病院じゃないんでな。こんな役立たずなキチガイはおいておけん」 お前もこいつの世話なんかまっぴらごめんだと言うなら、オレが始末をつけてやる。それぐらいの情けはあるさ。 彼女はそう言って、片方だけの目でオレをじっと見た。 案内された移動要塞の一室には、吐瀉物の悪臭が染み付いたベッドの上に、手足を鎖で繋がれた小さな妖怪が震えていた。 「どうする?」 もちろんオレは、二つ返事で引き受けた。 ***
彼の妹は、もういない。そして、氷河の国も、もうどこにもない。 それは、いわゆるクーデターだった。 彼女は氷った国を叩き壊し、木っ端微塵に砕いたのだ。 その伝統も、忌わしき決まり事も心根も、全て。 心通わぬ老いた者達を滅ぼし、望まぬ古き掟に縛られていた者達は解放した。 彼女は革命の女神になった。 そして、女神は革命の成功と引き換えに、命を落とした。 生き残った氷女の一人から聞いたところによれば、彼女は本当に怒りの女神のように、腐った国を見事なまでに滅ぼしたのだという。 まあ、正直そんなことはどうでもいい。 彼女も、氷河の国も、オレにとっては本当はどうでもいいことだった。 「……ぁ、ぅ」 また、ベッドの上の体がくの字に折れる。無理やり点滴で流し込まれている水分以外ろくに食べていないというのに、よくもまあこんなに吐けるものだとおかしな感心をしてしまう。 「う…あ、ぐ……げぇっ…!!」 えづく背中をさすってやりたいのはやまやまだが、先ほどの吐瀉物でオレの手はドロドロだ。 「飛影」 震える背中に、呼びかける。 「大丈夫?」 我ながら、なんという愚問だろうか。 「……くら…ま?くらま?」 その目。 赤い瞳。 オレを見るその目。 これは何もかも嘘だと、だたの冗談だと。 そう言ってくれと懇願する、目。 「飛影、君がいつまでもそんな風じゃあ、雪菜ちゃんが悲しむよ?」 一瞬、飛影の目に正気が見える。 自分の状況に今気付いたとでもいうように、赤い瞳がキョロキョロ泳ぐ。 「ね?お風呂入ろうか?少しは何か食べないと」 オレはシーツで手を拭う。 それだけでは到底綺麗になったとは言えないが、飛影の体に手を伸ばす。 背をさすってやりながら、オレは優しく、諭す。 「……くら」 「雪菜ちゃんはね、まるで女神様みたいに格好良かったんだって」 「………く、ら」 「でも」 でもどうして、雪菜ちゃんはオレたちに助けを求めてくれなかったのかなあ? 一人で国を滅ぼそうなんてさ、相談して欲しかったよね…。 オレは白々しく、そう囁く。 それがどれほどまでに彼にダメージを与えるか、よくわかっていて。 白い耳に、毒薬のように流れ込む言葉に、飛影が再び激しく震え出す。 壊したければ自分でやれと、生きているかもわからない兄に頼るなと、そう告げられた彼女がたった一人で計画を立て、見事なまでに実行したことをオレは知っている。 彼女にそう告げた者が誰なのかも、もちろんオレは知っている。 叱咤のつもりが最悪の結果を招くことになった言葉を彼女に告げた者は今、オレの腕の中で震えている。 恐怖と後悔と懺悔とが引き起こす、治まることのない吐き気に苛まれながら。 「……ぁ…ゅ…ゆき…雪菜…」 「オレたちだって桑原くんだって幽助だって、助けられたのに。助けたかったのに」 「……ゆ、ゅ…。あっぐ……あ、ぅ」 「どうして、一人で行ったんだろうね…? 」 「っぐ!!」 口元をおさえることさえせずに、ごぼっと嫌な音を立てて嘔吐する体を見下ろし、何度でもオレは言ってやる。 「…っう、あ、ぐ…げ…ぇっ」 「どうしてだろうね、飛影?」 どうして、オレたちに助けを求めてくれなかったんだろうね? そりゃあ、彼女は勇敢だ。でも、死んでしまっては何もならないのにね。 なぜ、彼女は一人でこんなことをしたんだろう? また、オレの手は汚れてしまっている。 彼の体、彼の腹の中で作られた温かな液体の感触、こっちまで吐きそうになるような悪臭にさえ、愛おしさしか感じない。 手のひらを、舐めてみる。 舌を刺すような嫌な苦味に、下肢が熱くなる。 「や、ああ…ぁ…あ…ゆき…」 「ほら、おいで飛影」 ここに来てからずっとしているように、今夜もオレは飛影を風呂に入れ、洗い清め、嫌がる彼に無理やり少しばかりの食事を摂らせるだろう。 いくらかの食物や飲み物が彼の中で形を変え、オレをぞくぞくさせる、ドロドロの液体になって戻ってくるのを期待しながら。 その楽しみに、子供のように目を輝かせながら。 「飛影?」 途方に暮れる赤い瞳が、すがるようにオレを見た。 ...End. エメトフィリア(嘔吐性愛) 嘔吐行為や吐き気、吐瀉物への性的嗜好。英語:Emetophilia |
Copyright RUMeRAL all rights reserved.
Since 2013 January
Since 2013 January