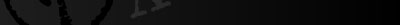*氷の国と銀の矢館はどの部屋も明るくはなかったが、今目の前が暗いのは、それとは違う理由のような気がした。胸がむかつく臭いに満ちたこの部屋に投げ込まれたのはついさっきで、石でできた床は横になるには冷たすぎて、俺は薄っぺらい布きれ一枚を纏った姿でがたがた震えていた。 「その部屋には入るな。蔵馬」 「なんで?いいじゃない。どうせ捨てるゴミなんだから」 どうやら廊下で話しているらしい。楽しげな声とともに開いた扉。 コツコツという足音が部屋をまわる。 「あ。死んでる。これも死んでる」 足音が、すぐ近くで止まる。 「…あれ?君はまだ生きてるんだね」 なんとか目を開けると、そこにあるのは、床に座り込み、俺を見下ろすエメラルドの瞳。 蔵馬は俺の右腕を取り、ガラス管から石を外す。 「うぅ…っ!!」 ガラス管を吸うように、蔵馬は口づけた。 とっくに感覚なんぞなくなっていると思っていた腕に、激痛が走る。 「ろくに出ないや。つまんないの」 投げ出すように、右腕が下ろされた。 呻いた俺に、蔵馬が話しかける。 「ねえねえ、死ぬってどういう気分?」 邪気のない、子供のような陽気な問いかけ。 自分が死にかけていることは薄々わかってはいたが、はっきり言われるのはショックだった。 「ねえってば。聞いてる?」 どうって。 どうと、言われても…。 寒い。 気持ちが悪い。 苦しくて…寂しくて… 「……こわい」 ぽつりとこぼした言葉に、蔵馬は驚いたように瞬く。 「…死ぬのは……こわい…死にたくない」 何がこわいのかは、自分でもよくわからない。 死は、どういうものなのだろう。 暗い場所なのだろうか。寒い場所なのだろうか。 そこには何が、あるのだろうか。 ……あるいは、何もないのだろうか。 「…ふーん」 目を開けているのも、苦しい。 けれど、この素晴らしい宝石のような瞳を、見ていたかった。 あらゆる植物の緑を吸い取ってできたかのような、エメラルドの瞳。 扉が外から、バン、と叩かれた。 「蔵馬、何をしている。出かける時間を考えて支度をしろ」 「うるっさいなあ」 「遅れることは許されんぞ」 「うるさい。だいたい、なーんで俺のお目付け役がよりによって、あんたみたいな口やかましいのなわけ?」 「一族の中で、お前が一番厄介者だからだろう」 もう一度扉を叩き、去っていく足音がした。 蔵馬は舌打ちをすると、立ち上がろうとし…。 「あいつ…むかつく…」 再び、座り込んだ。 「俺より低い身分のくせに、えっらそうに」 なんだか、部屋が一層寒くなったような気がした。 目を閉じ、なんとか呼吸をする。 寒くて、寒くて、歯の根も合わない。 猛烈に吐き気がするというのに、えづいても出てくるものもなく、ひどく苦しい。 「ねえ」 もう、返事もできない。 この綺麗な生き物をもっと見ていたかったのに、目を開けることも、もうできない。 「目を開けてよ」 できない。 もう、何も 「…死にたくないんでしょ?」 手が伸ばされる気配を感じた。 だが、その手は右腕ではなく、両方の脇の下に入れられた。 体が持ち上げられ、服が脱がされ、蔵馬の上に座らされるのをおぼろげに感じる。 「…ねえ、助けて…あげようか?」 「……?」 膝に手を回され、両足が大きく開かれた。尻の奥に何かが当たる。 指一本動かすこともできずに、人形のようになすがままになっていた、その瞬間。 「ーーーっ!! ひあ…」 尻の穴がぐっと開かれ、何かが押し込まれた。 長くて硬い、棒のようなもの。 冷たくて、得体の知れないもの。 「んんんんーーっ!! んっう!うあぁぁぁああ!!」 「…あったかーい」 耳元で、くすくす笑う声。 痛いと言葉にする間もなく、体が上下に揺さぶられ、冷たい棒が尻の中を行き来する。 「うう!! うっうっうっ…うあ!!」 「目を開けてよ」 「うあ!ぁああ、あああ…っ!!」 「目を開けろって言ってるんだよ」 渾身の力を振り絞って、なんとか目を開けた。 頬に触れるほど近くに、エメラルドはあった。 エメラルドの瞳。 綺麗な鼻筋、薄く形のいい唇。 その唇が開き、尖った…とんでもなく尖った… 「あああぁぁぁぁぁああ!!」 首筋が、熱い。 突き立てられた、尖った歯。 これだけの血が、体のどこに残っていたのだろう? 熱い血がどっと噴き出した。 「あぁああ!! あ、ああ…」 ごくりと、のどを鳴らして。 蔵馬は俺の首にむしゃぶりついている。 体を上下に揺さぶる動きは、少しも休まずに。 「うあ!! あぁ…ひっう!」 尻の中、奥の奥に、何かがどろっと広がる。 冷たい、冷たい液体が、体の中に…。 「あ……っあ、ああ、ああぁぁ…?」 ふいに、目の前を覆っていた霧が、さあっと晴れるような気がした。 手に足に指先に、体中に一瞬力が戻り、俺は目を見開いた。 ちゅぱ、と濡れた音を立て、蔵馬の唇が首筋から離れる。 感極まったかのようなため息が、傷口にかかる。 「やっぱり…君はすごく美味しい」 「……き…さま!!!! 貴様…っ!!」 腰を上げ尻の中に突き立った棒を引き抜き、目の前の男を思い切り突き飛ばした。 壁にぶち当たるほどの勢いだったというのに、男は何事もなかったかのように、壁に寄りかかり、笑いながらこちらを見ている。 「……ヴァ…ン…パイア!!」 瞳孔のないエメラルドの瞳。 異形の者の、瞳。 ついさっきまで、この男を好きだった? 俺が!? この男を!? 愛していた? 冗談じゃない!! なぜこんなことに!? 「あらら。正気に返っちゃった?」 ニヤニヤ笑ったまま、髪をかき上げる。 いまいましい、人殺しの血吸い野郎。 なぜ…? なぜこんなことになった!? ***
永く永く問題を抱えていた、俺の国。 ***
雪菜が発って、三日が経った。家事を終え、テーブルの上の毛糸を眺める。 ほんの少しだけ手に入った貴重な毛糸は隣に住む婆さんが俺にとくれた物だった。コートはおろか、マフラーにするにも足りないであろう毛糸の束。俺の元には、救世主への貢ぎ物とでも言うべき、布や毛糸、食べ物といった贈り物も多かった。 貰った物をどう使おうが俺の勝手だ。雪菜に何か作ろう。 これで作れるのは、せいぜい手袋か帽子だ。もっとも、弓にしろ剣にしろ、手袋をしていては使いにくいと、きっと雪菜は言うだろう。 雪菜に似合うとも思えない橙色の毛糸だったが、帽子にしようと決め、編み棒を探しに地下室へ降りた。 ごたごたと、物が積み重ねられた地下室。 思い当たる場所を探してみたが、編み棒は見当たらない。そもそもこの国では毛糸でさえろくに手に入らない。以前に編み棒を使ったのは半年も前のことで、どうにも見つからなかった。 いらいらしながら、あちこちの箱を探す。 窓のない地下室では当然蝋燭が必要だったし、蝋燭も貴重品だ。無駄に使いたくなかった。 「…くそ」 ぼやきながら、一番上の棚の破れかかった布を取り、見覚えのない粗末な木箱を開けた。 箱の中身は、思いがけないものだった。 きちんと額に入った小さな肖像画。顔は覚えていなくとも、雪菜にうり二つの顔は俺たちの母親、氷菜なのだろう。 肖像画とはまたけったいな。育ての母であった、泪の持ち物だったのだろうか。 …その泪も、もういない。 泪が死んだのはヴァンパイアとは関係のない、三年前の雪崩で起きた川の堤防の決壊のせいだった。決壊した川の流れをくい止めるために出かけた泪は、他の女たち同様、任務を果たし、帰らぬ者になった。 蘇った笑顔に、胸が痛んで、しばらく呆然としていた。 泪は優しくて、強い女だった。 母親の氷菜は出産で命を落とした。氷菜の親友だったという理由だけで、ずっと俺たちを母親代わりに育ててくれた。 のばした自分の指先さえ見えなくなるような吹雪の中、泪は笑って出かけていった。 私は大丈夫。死んだりなんかしないわ。 あなたたちを残して死んだりなんかできない。 そう言い残して。 ふいにその言葉が三日前に妹の口から発せられた言葉と同じことに気づき、ぞっとする。 「…あつっ」 指に落ちた蝋に、我に返った。 思い出に浸るのは、貴重な蝋燭を使っている間でなくてもいい。 肖像画を戻そうとした手に、小さな袋が触れた。カチャンと金属音がし、重みがある。 朽ちかけたぼろぼろの袋を開けると、中身はスプーンとフォークが、三本ずつ入っていた。何かの祝いの品なのか、丁寧な彫刻がなされている。 だが、そんなことはどうでもいい。これは。 「…銀だ」 驚きと、地下室の寒さに声が震える。 銀製品を見るのは、何年ぶりだろう。 元々高級品である銀はあまりこの国にはなかった。銀製品を持っていた者は強制的に没収され、武器の補強に使われた。 ヴァンパイアを倒す唯一の方法が、銀を使った道具で胸を射ることだと言われていたからだ。 見つけた銀は、街の長老に渡すことになっていた。 けれど、でも。俺は。 …雪菜に渡したかった。 矢の先端を銀で覆った矢が、弓の名手たちに配られてはいたが、それは一本ずつだった。 当然、雪菜の持つ銀の矢も一本だ。 これは、氷菜か泪の持ち物であることは間違いない。 なぜ、街中で分け合わなければならない?これを使う権利は、雪菜にある。 雪菜が持っている銀の矢だって、誰かの銀を使ったものだ。 自分でも勝手な理屈だとはわかっていた。 階段を駆け上がり、わずかな薪で暖炉に火をおこした。 ***
そこからの記憶は、あやふやだ。家にあった十五本の矢の矢じりを、溶かした銀で覆い、身支度をして家を出た。 そして…? 何が…あった? どうして俺は、こんなところに? 笑いながら、こちらを見る男。 そう年は違わないだろう。 漂う悪臭に部屋を見渡せば、転がるいくつもの腐りかけの死体は、赤い瞳をしている。 俺の国の女たちだ。 思わず後ずさり、悪臭に鼻と口を手で覆った。 なぜ? なぜ気づかなかった?こんな男に血を吸われたくて、憎みあい争っていたのは俺の国の女たちじゃないか。 いったい俺は、どうしたっていうんだ!? 「俺たちに血を吸われると、みんな恋に落ちるんだよ。君みたいにね」 心を読まれたかのような言葉にぎょっとする。 男はまだ笑っていた。 「貴様……」 こいつに、いや、こいつらに、か? いったい何人何十人何百人が殺されたことか。 「殺してやる!!!」 「へー。どうやって?」 銀はおろか、ナイフすらも持っていないことはわかっている。だいいち服すら着ていない有様だ。 だからって、何もせずにはいられない。 「かっかしないでよ。君はもう俺たちの仲間なんだから」 「何を言っ…」 全身に鳥肌が立った。 首筋に手を当てると、手のひらは真っ赤に染まった。 ヴァンパイアに血を吸われた者はヴァンパイアになる。 じゃあ、俺は…俺は……? 「まあ厳密には、血を吸うだけじゃならないんだけどねー」 心を読まれている、それはもう確かだった。 「そ。正気に返った今、君の心は完璧に聞こえる。そして君はもうヴァンパイアだ。おめでとう」 「ふざけるな!」 大声を上げた途端、荒々しい足音がした。 「蔵馬!行くぞ!面倒なことになっ…」 角の生えたその姿は、正気に返った今となってはあきらかに異形の者だった。 盲であることは間違いはないようだが、まるで見えているかのようにこちらを凝視する。 「蔵馬……まさか…まさか!その者を!?」 「そうー。いいでしょー?俺の子だよ」 「愚か者!!!!」 空気をびりびり震わせるような怒声にも、蔵馬はしらっと笑う。 子供じみた喋り方だというのに、笑みは無邪気なものではなく、とても嫌な笑みだった。 「馬鹿な!! お前はまだ子を作る資格など得ていない!! しかもこのような下賎の者を!!」 「何とでも言えば。もう手遅れだよ」 嫌な笑みを、蔵馬はこちらへ向ける。 笑う口元から、鋭い犬歯が覗く。 「飛影、君はもう人間じゃない。ようこそ、我らが世界へ」 ...End. ヘマトフェリア(血液性愛) 血液を見ることで性的快感を覚え、血液に対して異常な執着を見せる一種の精神病。一般的な性行為では満足を得られず、血を見なければ満足を得られない状態になると「血液淫虐症(ヘマトディプシア)」と呼ばれる。英語:Hematphiria |
Copyright RUMeRAL all rights reserved.
Since 2013 January
Since 2013 January