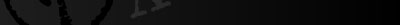*お好きに召しませエメラルドでできた碧の瞳が、いくつかのランプの灯だけの部屋をゆっくりと見渡す。こちらから声をかけることは禁じられている。 声をかけてもらえることをただただ願って、十三人分の視線が、暗褐色のソファと、そこに座る者に注がれる。 胸が、どくどく脈打つ。 大丈夫だ。自分にそう言い聞かせる。 このところずっと、もう十日以上も、指名されているのは俺だ。 だから、大丈夫。きっと、俺を。 たくさんの彫刻が施された壁の前に立つ、十三人。 名を呼ばれるのは、一日にひとりだけだ。 「…飛影、おいで」 安堵と喜びに、思わず小さく声を漏らす。 怨嗟と憎悪に満ちた十二人分の視線が俺に突き刺さった。だがそれも快感でしかない。 ソファの前に立つと、髪に頬に唇を、いい匂いのする指がすべるように撫でていく。 それだけで、下腹部にぞくぞくと震えが走る。 「お前の瞳は、本当にルビーのようだね」 耳の中に、吹き込むように囁かれる。 背の低い俺は立ったままでも、ソファに座ったままの相手と、顔の位置はそう変わらない。 間近で見つめるエメラルドに、吸い込まれそうだ。 「…蔵馬」 好きだ。 どうしてこんなにこの男のことが好きなのか、わからない。 好きで、好きで、好きで。 この瞳を見るだけで、気が狂いそうになる。 「脱いで、飛影」 長さは足首まである、すとんとかぶるだけの白い服は、胸元と腰の細い紐を解くと、するりと脱ぐことができる。 裸になった俺を、蔵馬は両腕に抱いた。ソファに腰掛けた体をまたぐように座らされる。 裸の背に、選ばれなかった者の視線。 後であいつらにどんな目に遭わされるかはわかっているが、だからといってこの立場を譲ろうなどとは微塵も思わない。 今夜も選ばれたのは俺なのだ。 歓喜に、頬が熱くなる。 蔵馬が、俺の右腕を取る。 動脈に埋め込まれたガラスの管は、すべすべと丸い石で栓がしてある。 テーブルに置かれたグラスを、蔵馬は手にする。 丸い石が弾かれ、ガラスの管からは鮮血があふれ出した。 「……んん」 ごく小さなグラスの半分ほどに、紅色の液体が注がれる。 「ん……く…らま」 かちんと、管に石が戻される。 俺を膝に乗せたまま、蔵馬はグラスをランプの灯に翳す。 「綺麗。いい香り」 蔵馬はうっとりと呟くと、グラスに薄い唇をつける。 優雅で、それでいて貪欲に、グラスを干す。 舐めたわけでもないのに、グラスに一滴の血も、それどころか血の汚れすらも残っていないのは、いつものことながら少し不思議だった。 「ああ…美味しい」 素直な、本当に嬉しそうなその言葉に、俺も嬉しくなってしまう。 名残惜しそうにグラスを置いた蔵馬が言う。 「ねえ。行儀悪いこと、してもいい?」 子供っぽく、ねだるその顔。 俺が頷くのも待たずに、蔵馬は右腕を取り、ガラス管から垂れ、腕を汚した血を舐める。 あたたかい舌が、ねっとりと腕を舐める。 ガラス管に異常に尖った犬歯がぶつかり、かちゃかちゃと音を立てた。 腕から下腹に、ぐうっと熱いものが通る。 我慢、できない。 蔵馬の纏う絹の衣装に、俺は精液をぶちまけた。 「……あ」 黒い絹が、どろりと汚れる。 謝ろうと顔を上げると、笑みを浮かべた蔵馬と目が合った。 「いいよ…許してあげる。そのかわりもう一回ちょうだい?」 「…蔵馬、もうやめておけ」 ソファの後ろの暗がりに、闇に溶け込むようにして立っていた男が、今夜初めての言葉を口にした。 男は大柄で何本もの角が生えている。口をきくところは滅多に見ない。盲だという噂だが、身のこなしからはとてもそうは思えなかった。 「同じ者から採るなと言っているだろう。このところそいつばかりから飲んでいる」 「いいじゃない。もう一回だけ」 「やめておけ。一匹だけから飲むと、廃棄処分が早まるぞ」 「だってこの子、すごーく美味しいんだもの」 甘ったるい声で、蔵馬は言う。 「ね?もう一回だけ」 「…勝手にしろ」 俺に視線を戻した蔵馬が、微笑む。 再び石が外され、グラスが満たされる。 「……うぅ…っ」 体温が下がるかのような寒気とともに、急激に吐き気が込み上げた。 ガラス管に栓をすると、蔵馬は俺を見ることもなく、嬉しそうにグラスに口を付ける。 寒い。気持ちが悪い。 蔵馬にしがみつくこともできず、ずるずるとすべり落ち、俺は床に蹲った。 喜びや期待とは全然別の、鼓動。悪寒。 脂汗が滲み、吐き気とめまいに、胸が早鐘のように打つ。 ランプの炎が揺らぎ、すうっと目の前が暗くなる。 ***
「ずいぶんと気に入ったものだな」頭上の声に目が覚めたが、気分の悪さに目を閉じたままでいた。 どうやらソファに座った蔵馬の膝枕で、眠っていたらしい。絹の布越しに感じる蔵馬の肌は、とても冷たい。 「極上だよ。とろっと甘くて、すごく美味しいんだ」 「それはそれは。だがもうそいつはそろそろ死ぬぞ」 ソファの背によりかかった男が、こともなげに発した言葉の意味が、よくわからない。 誰が、死ぬのだろう? 「死んじゃうかな?」 「ああ。わかっているだろうが」 「嫌だな。こんなに美味しいの、滅多にないのに」 蔵馬の指が、俺の髪を引っ張る。 「なら加減しろ。しばらく他の者から飲め」 「えー?嫌だよ」 「わがままを言うな。三日ずつでもあければ、もう百日くらいは持つだろう」 「はぁぁい」 間延びした返事をし、蔵馬は俺の頬をつまむ。 「あと百日だって。さみしいなあ」 くすくす笑う、声。 ゆっくり瞼を開けると、エメラルドが目に飛び込んできた。 「……蔵馬」 「ああ、起きたね。食事中に気を失うなんて、困った子だね」 「すまない…」 俺を床に下ろすと、蔵馬はさっさと立ち上がる。 先に立った男が開けた扉を抜け、去ろうとする蔵馬に、思わず声をかけた。 「…蔵馬!」 「なあに?」 振り向いた拍子に、絹よりもなめらかな黒髪が、さらさらとすべる。 頭のてっぺんからつま先まで、綺麗で。 この男が、好きで好きで。 ふいに、泣きたくなった。 「……好き…だ。蔵馬」 「知ってるよ」 花が咲くような笑みを残し、扉が閉ざされる。 後を追い、踏み出した途端、猛烈なめまいに座り込んだ。 「蔵馬……」 テーブルに置かれたままの、グラス。 右腕のガラス管から石を外し、グラスを押し当てた。 グラスを満たし、グラスからあふれ、硬い木の床に赤い染みがみるみる広がる。 視界がかすみ、鼓動はもはや胸を破裂させるような勢いだ。 「……ん」 ソファにつかまり、なんとか立ち上がる。 扉までのほんの十歩ほどが、信じられなく長い。 グラスの中身をこぼさぬよう、震える両足を叱りつけ、一歩ずつ、進む。 腕が、体が、熱い。 ふと見下ろせば、栓をしていないガラス管から滴る血が、全身を染めていた。 グラスにはなみなみと、紅色が満ちている。 きっと蔵馬は、喜んでくれる。 指先からグラスがすべり、足下で砕けた。 足先に、あたたかな飛沫。 細かに鋭く割れたグラスの上に、裸のままの体が倒れる。 噴き出す血潮は、熱く甘い。 「…くら……」 きっと蔵馬は喜んでくれるだろう。 体中を染める血を、一滴も余さず、舐めてくれるだろう。 美味しいと、笑ってくれるだろう。 「………くらま」 幸福なため息をついて、俺は目を閉じた。 ...End. ヘマトフェリア(血液性愛) 血液を見ることで性的快感を覚え、血液に対して異常な執着を見せる一種の精神病。一般的な性行為では満足を得られず、血を見なければ満足を得られない状態になると「血液淫虐症(ヘマトディプシア)」と呼ばれる。英語:Hematphiria |
Copyright RUMeRAL all rights reserved.
Since 2013 January
Since 2013 January